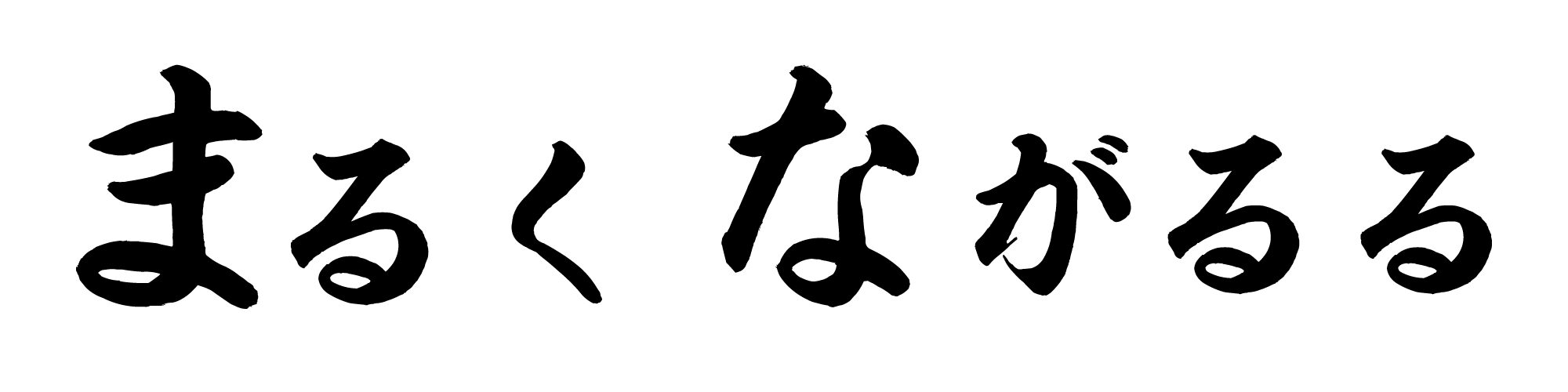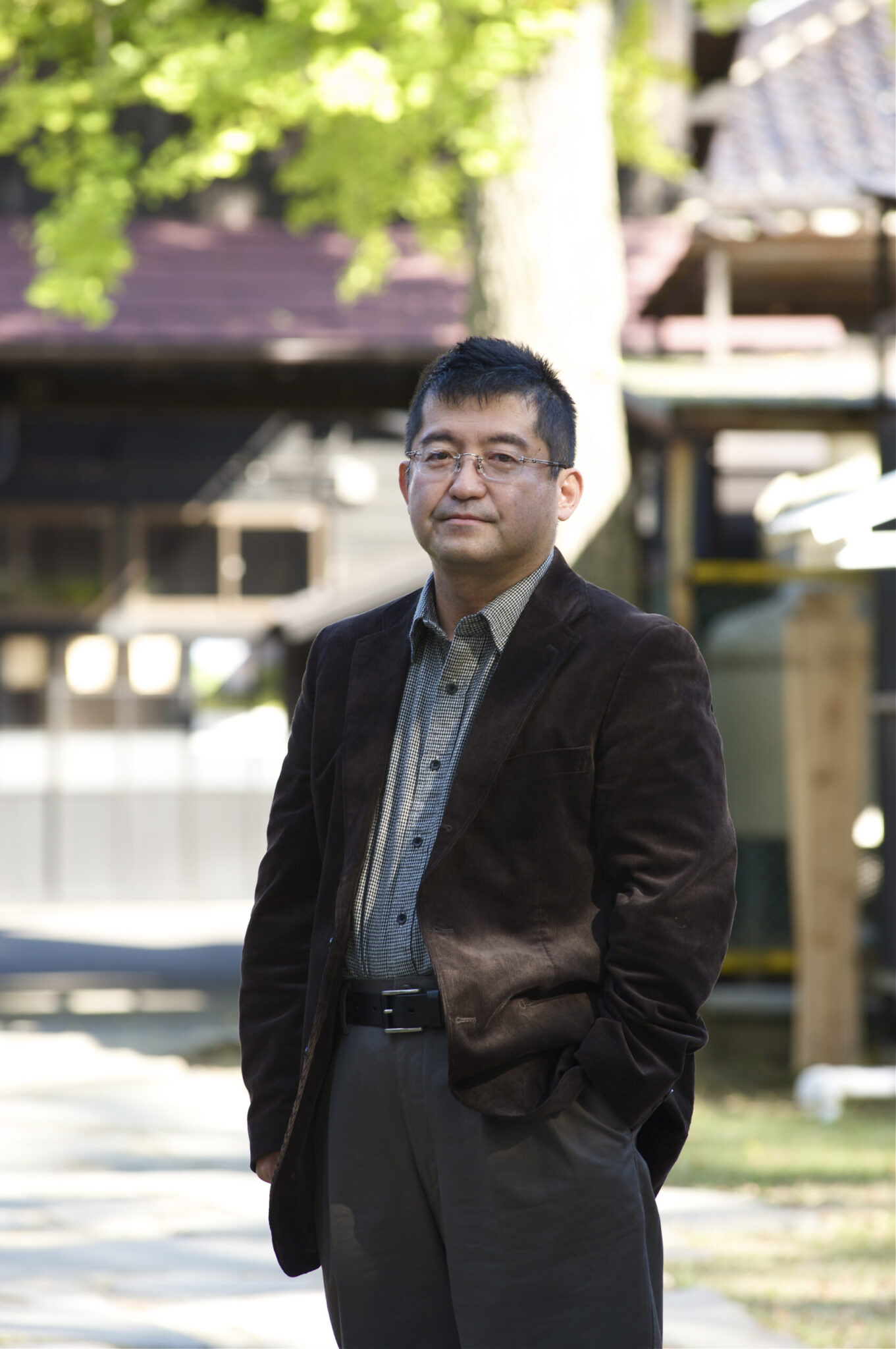- 陰口を言ってしまう理由
つい言っちゃう「陰口」の心理。それ、心のSOSかもしれません。「あの人ってさ...」 気づいたら、誰かの悪口を言っていた。そんな経験、ありませんか? |後から「なんであんなこと言っちゃったんだろう」って後悔する。でも、また同じことを繰り返してしまう。そんな自分に自己嫌悪...。 実は、陰口を言ってしまうのには、ちゃんとした心理的な理由があるんです。今日は感情知能EQの視点から、その仕組みを紐解いていきますね。続きをみる
- 理屈ではわかっているのに感情が邪魔する人
「頭ではわかってるのに動けない」のは、意志が弱いせいじゃなかった続きをみる
- 成功した友人への嬉しさと嫉妬の感情
友人の成功を素直に喜べない自分が、実は「正常」な理由続きをみる
- ご褒美依存の怖さ
その「ご褒美」、あなたを縛る鎖になってませんか?続きをみる
- SNSで得られるもの・得られないもの
SNSの「いいね」では満たされない理由、知っていますか?続きをみる