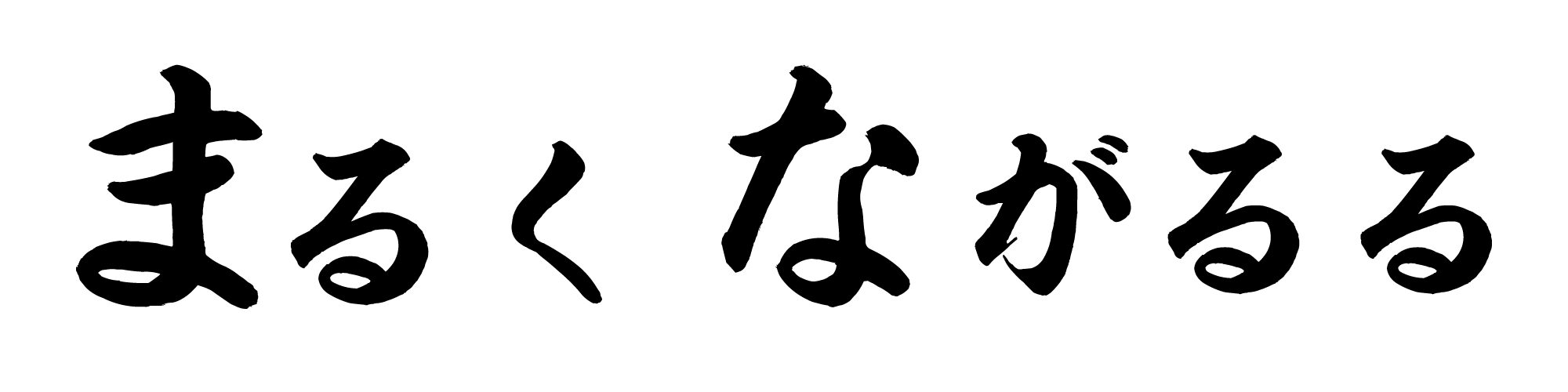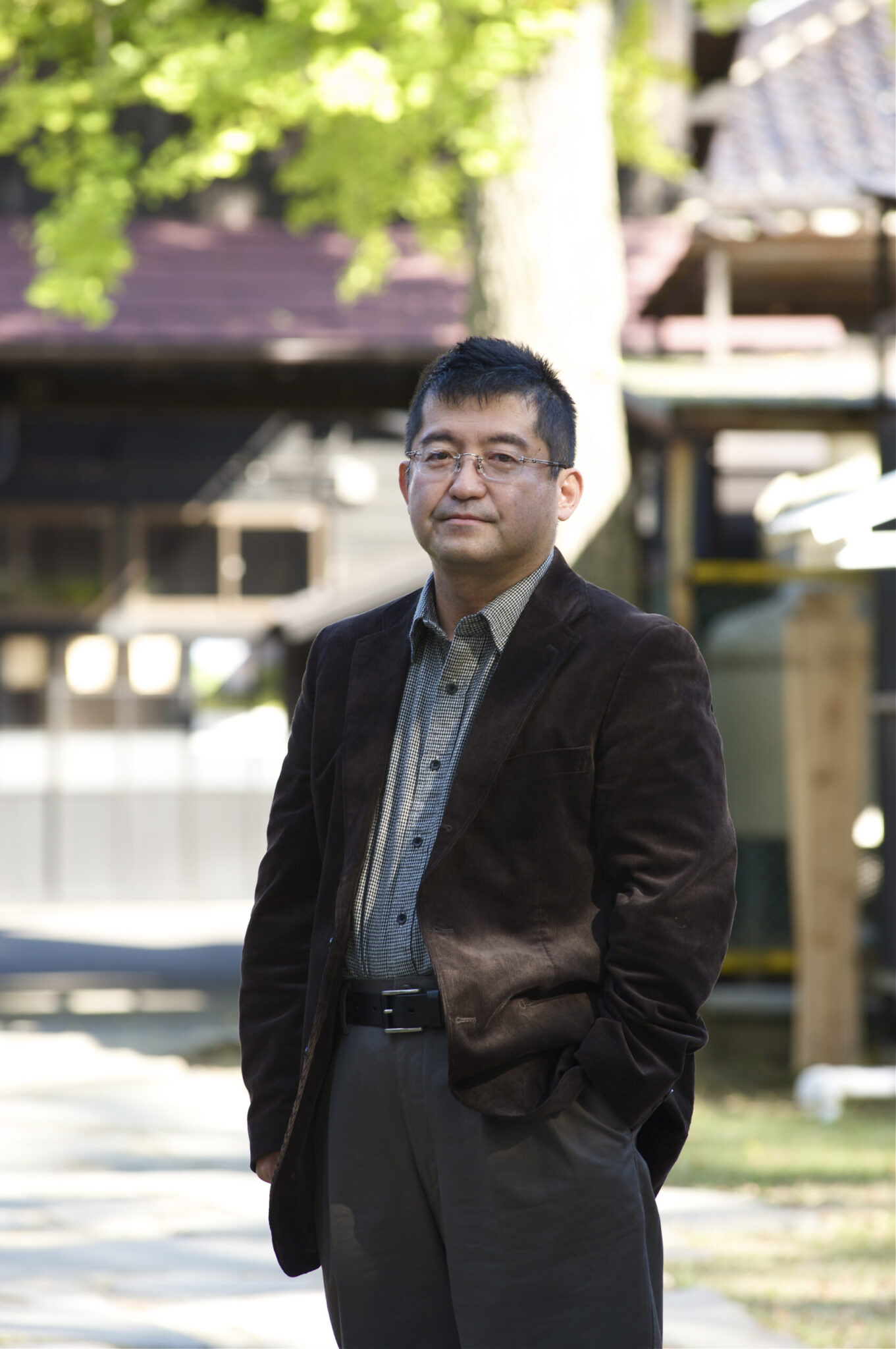騒乱の村での生活が始まって数週間。カイは初めこそ驚きと戸惑いに翻弄されていたが、少しずつこの村のリズムに馴染んできた。朝起きれば隣家の陽気な歌声や夫婦喧嘩の声が聞こえ、昼になれば広場で音楽と踊りが繰り広げられる。夜は夜で、一日の溜まった感情を発散するかのように、笑い声や泣き声、怒声が混ざり合う。しかし、不思議とすべてが混然一体となり、この村の人々の“活力”を支えているように感じられる。
カイは積極的に人々と話をするように心がけた。怒りっぽい大工の男は、道具が思い通りに動かないとすぐに怒鳴り散らすが、同時に仲間が苦しんでいるときは、涙を流して共感するほど優しい面もあった。情熱的な踊り子の女性は、時には嫉妬心をむき出しにするが、一方で仲間の幸せを心から喜び、抱き合って笑う瞬間も見せる。
――どうやら、ここの人々は一面だけで判断できるほど単純ではない。怒りも悲しみも、喜びも愛情も、すべてが混ざり合って一人の人間を形成している。その生々しさを、カイは肌で感じていた。
ある夕方、カイはイオと一緒に広場で行われる小さな集会に参加することになった。話し合いの議題は、次の豊作祭をどう盛り上げるかというものだ。カイからすれば、祭りの企画とはなんと楽しそうなテーマだと思うが、騒乱の村の集会は一筋縄ではいかないらしい。
広場に集まった十数人の村人は、既に熱く議論し始めている。
「もっと派手な音楽を用意しろよ! 太鼓の数が足りないだろう!」
「いやいや、そんな予算はどこにもないよ。まずは祭りの準備に使う材料を確保するのが先だろう!」
「それなら装飾は最小限にして、食べ物をいっぱい用意しろ。見栄えばっか気にしても腹は膨れねえ!」
声が入り乱れ、怒鳴り声と賛同の声、ため息や笑い声が同時に飛び交う。カイはその光景を目の当たりにして圧倒されるが、ふと気づく。
――彼らは一見ケンカをしているようでいて、互いの意見を否定し尽くすわけではない。時には「あんたの言うことも一理ある」と相手に寄り添っている。
カイは思いきって発言してみようと思った。静寂の村の人間が、ここで口を出したらどうなるだろう? 胸が高鳴り、手が震える。けれど、イオがそっと背中を押してくれた。
「みなさん、すみません。僕は静寂の村から来たカイといいます。まだこっちのやり方には慣れていませんが、もし意見を言わせてもらえるなら……」
一瞬、周囲が静かになる。ざわざわとした空気の中で、誰かが「おう、何だ?」と声をかける。カイは深呼吸をして、自分の中にある考えを言葉にした。
「僕は感情を抑える村で育ちました。でもここでの皆さんの様子を見て、感情をぶつけ合うことが必ずしも悪いわけじゃないと気づきました。むしろその衝突の中から、新しいアイデアや理解が生まれていると思うんです。だから、この豊作祭の企画でも、お互いが納得いくまで感情を出し合い、同時に理性的に落とし所を探すことができたらいいなと……」
そう言い終えると、村人の一人が腕を組んでにやりと笑った。
「理性的な落とし所、ねえ……面白いこと言うじゃねえか。こっちは感情のまま突っ走るのが常だけど、それだけだと祭りが終わった後に大喧嘩になることも多い。お前の“静寂の村”のやり方を、ちょっと見せてくれよ」
周囲からも「理性だって?」「面白そうだな」「そんなのうまくいくのか?」など、様々な声が上がるが、総じて否定的ではない。むしろ興味津々といった空気だ。
カイは不思議な感覚を覚えた。静寂の村で生まれ育った自分の考えが、騒乱の村の人々に受け入れられるかどうかはわからなかったが、少なくとも今この場では“新しい意見”として興味をもたれた。抑圧の世界と解放の世界――その二つを知るカイだからこそ、何かできることがあるのかもしれない。
こうして、豊作祭の企画会議は感情むき出しの激論と、カイの提案する“冷静な妥協点の探り方”が混じり合う形になった。時にカイ自身も感情をあらわにしそうになりながら、しかし静寂の村で培った自制心を生かして言葉を選ぶ。周囲の人々は怒ったり笑ったりしながらも、カイが示す理性的なプランに耳を傾けてくれた。
会議が長引き、やがて夜になった。最後には「よし、今回だけはカイの方法を試してみようか」ということで、ある程度の合意が得られた。村人たちは口々に「疲れたー!」と叫びながらも、笑い合って解散していく。イオは誇らしげにカイの肩を叩いた。
「よくやったじゃないか、カイ。初めてなのに、ちゃんと自分の意見を言えた」
カイははにかんだように笑みを返す。
「ありがとう。でも、正直、僕もみんなの熱気に当てられて、心がぐらぐら揺れたよ。でも、それが“生きている”っていうことなのかな……って思うと、不思議と怖くなかった」
ふと、カイは頭をかすめる疑問を口にする。
「もし静寂の村の人たちが、今ここにいたらどう思うだろうね。こんなに感情をむき出しにして、怒鳴り合ったり笑い合ったりする姿を見たら、驚くかな?」
イオは少しだけ目を伏せ、微笑みながら答える。
「最初は“なんて無秩序なんだ”って思うだろうけど……もしかしたら、心のどこかで“羨ましい”と感じるかもしれないね。僕はそう信じてる。だって、人間って感情がある生き物なんだから」
二人はそんな会話をしながら、夜の街を歩く。騒乱の村の空は、やかましい音とともに星が輝いていた。
その夜、カイはまた夢を見た。今度は静寂の村と騒乱の村の人々が、一つの広場に集まっている。誰もが最初は戸惑いの表情を浮かべているが、やがて少しずつ言葉を交わし、相手の感情を受け止め始める。どこからか音楽が聞こえ、静かだった村の人たちも、そのリズムに合わせて身体を揺らし始める。騒乱の村の人たちは、その姿を見て涙を流しながら笑っている。
――そんな不思議で、美しい夢だった。
目覚めたとき、窓の外では朝陽が昇り始めていた。騒乱の村の一日は、また今日も喧騒と笑い声に包まれて始まる。カイは胸に湧き上がる確信を感じながら、そっと小さく呟いた。
「理性と感情、静寂と騒乱……どちらも大切で、どちらも欠かせない。いつか僕は、この二つを繋ぐ架け橋になれるだろうか……」
カイとイオ、そして静寂の村と騒乱の村を取り巻く物語は、まだ続いていく。感情が完全に欠如した「虚無の地」と、感情が制御不能になった「混沌の荒野」がどこかに存在するという噂も、いつか彼らをさらなる旅へと誘うだろう。その先に待つのは、人間らしさの究極の姿か、それとも破滅なのか。
いずれにせよ、カイはもう迷わない。理性を大切にしながら、同時に自分の感情を押し殺さず、他者の感情とも触れ合って生きていく道を切り開きたい――それが、今の彼の確かな想いだった。