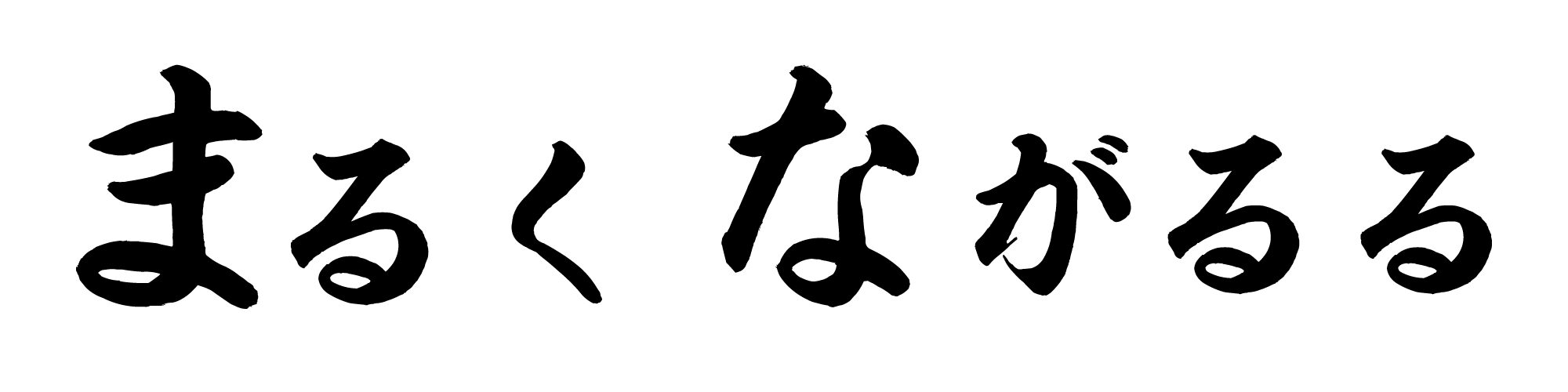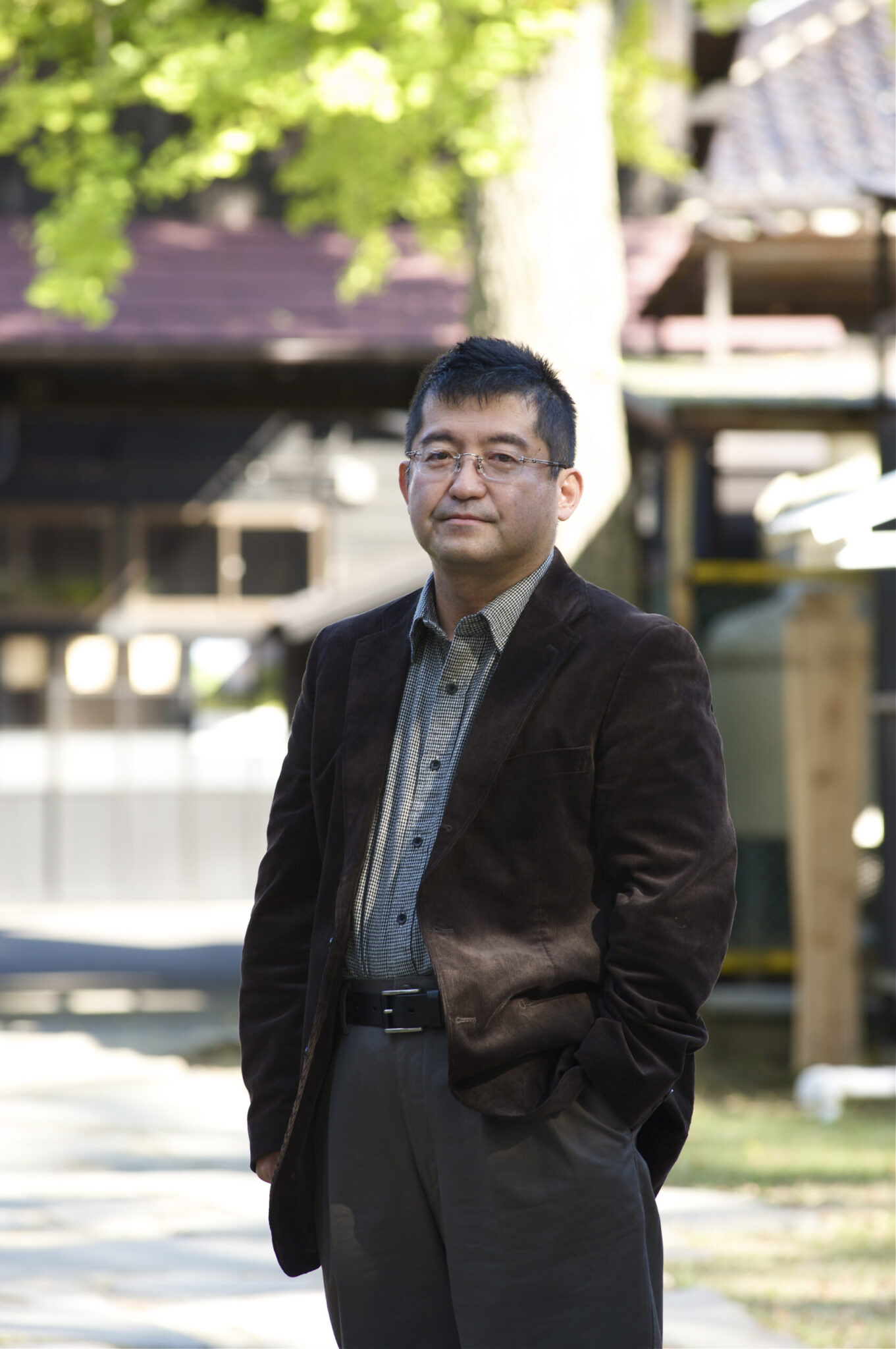翌日、カイはいつになく早起きをし、朝焼けの街並みを見渡しながら自宅を出た。頭の中には、昨夜イオと語り合った言葉が渦巻いている。
「……感情を押し殺していると、本当の自分に気づかなくなることがあるんだろうか……?」
外では寒々しい風が吹いているが、心の内は妙に落ち着かず、じわじわと熱が広がるようだ。
今日は特別な日だ。カイはイオを自宅に招くことにしたのである。静寂の村の習わしとしては非常に珍しい行動だが、村外から来た客人だからこそ許される余地があると考えた。
カイの家は村の外れ、少し高台になった場所にある。木造の小さな家で、窓辺からは遠くの山々まで見晴らすことができる。イオが来る約束の時刻になると、控えめなノックの音が聞こえた。
「どうぞ」
カイが扉を開けると、イオが興味深そうに周囲を見渡しながら入ってくる。
「この村の住宅って、どこも落ち着いた佇まいだね。騒乱の村は色彩も派手で、家々から音楽や笑い声が絶えないから、ちょっと面食らうよ」
そう笑いながら言うイオの言葉に、カイはほんのわずかな嫉妬と憧れを感じた。音楽や笑い声が常に聞こえる村――それは静寂の村からすれば、まるで異次元のようだ。
家の奥の部屋でカイは、温かい飲み物を用意しながらイオに尋ねた。
「ねえ、イオさん。騒乱の村の暮らしって、やっぱり大変なの? 感情が常にぶつかり合うってことだよね?」
イオはふと真顔になり、手元の湯呑みを眺めながら応える。
「そうだね。喧嘩や口論は日常茶飯事だし、すぐ怒ったり泣いたり、抱き合って喜んだり……とにかく忙しいよ。だけど、不思議と嫌じゃないんだ。それが、たとえば不合理であっても、そこに人間らしさや活力を感じる。僕自身は、その荒々しさの中でこそ、新しいアイデアや独創的な発明が生まれると思っているんだ。」
その言葉を聞きながら、カイは何度も頷く。静寂の村では想像もつかないような光景だが、イオの話を聞くと否定的な思いよりも、“見てみたい”という好奇心が湧いてくる。
一息ついたあと、イオは逆にカイへと問いを投げた。
「カイはどうして感情に興味を持ったの? それだけ抑圧されてる村で育ったからこそ、むしろ興味が湧いたわけ?」
カイは少しだけ視線を床に落としながら、言葉を選んだ。
「……子どもの頃、僕はあることで泣きたくなったんだ。でも、親や先生に“泣くのは恥ずかしいことだから、家で一人の時に泣きなさい”って教わって、学校ではぐっと我慢してしまった。でもそれからというもの、自分が本当に泣きたいのかどうかも分からなくなって。心がどこか麻痺したようになったんだ。」
そのときのカイの声は微かに震えていたが、ゆっくりと先を続ける。
「理性は大切だと思う。でも、理性だけじゃどうにもならない時があるんじゃないか……そんな気がして、僕は感情の研究を始めたんだ。」
イオはそれを聞いて、大きく頷いた。
「感情は面倒でもあるけど、やっぱり人を生かす力でもあるよ。僕はそう信じている。騒乱の村は確かに衝突だらけだけど、その衝突があったからこそ、分かり合えたり、思いやりが生まれたりする瞬間もあるんだよね。」
会話が続くにつれ、カイは心の奥底から言葉が湧き出してくる感覚を覚えた。自分の村では決して経験できなかった、この“自然な感情のやり取り”。その心地よさと、それでもまだ残る微かな不安が胸を交錯する。
――感情を抑えてきた人生と、感情を自由に表現する生き方。どちらが正しいのかはわからない。でも、人として生きる上で、どちらも捨てがたい面があるように思える。
やがて、静寂の村ならではの昼時の鐘が鳴った。重々しい一音が遠くの丘から響いてくると、イオが顔を上げる。
「少し外を歩いてみないか? この村の景色をもっと見たいんだ。」
カイは頷き、共に家を出る。午後の陽射しが村の石畳を優しく照らしている。呼吸をするたびに空気が透き通っているようで、イオも思わず感嘆の溜息を漏らした。
「こんなに透き通った空気、騒乱の村じゃ滅多に感じられないよ。あっちは常に人の声や楽器の音がこだましてるからね。どこもかしこも活気に溢れてる分、空気がザワザワしてるんだ。」
イオの言葉に、カイは複雑な思いを抱く。静寂の村では喧噪はなく、日々は落ち着いている。それ自体は素晴らしいと思うけれど、イオの話を聞くうちに、“喧噪”がもたらすエネルギーや歓声がどんなものか、想像してみたくなるのだ。
歩きながら二人は、村の中心部へ向かった。そこには大きな噴水があり、かすかな水音が広場に広がっている。人々が行き交う中でも、静寂の村の住民は言葉少なに、小さな会釈や目配せで挨拶を交わす。イオは興味津々に辺りを見渡しながら、カイに尋ねた。
「この人たち、怒ったりすることはないのか? 文句を言いたくなるときはどうしてるんだろう?」
カイは少し苦笑い気味に答える。
「怒りそうになったら、その場を離れるか、時間をかけて冷静に言いましょうっていうのが村の教えだ。対立自体は表面化しにくいけれど、その分、心の中にわだかまりが残ることもあるみたいだね。」
イオは噴水の縁に腰を下ろし、真剣な表情で水面を見つめた。
「感情って抑えても、どこかに蓄積してしまうものだよな。その蓄積が、何かの拍子に大きな爆発を起こすこともある…騒乱の村では爆発が日常茶飯事だから、逆にそれが“ガス抜き”になってるのかもな。」
その言葉を聞き、カイの胸にはまた一つの疑問が浮かぶ。
――静寂の村で過ごす人々は、本当に感情を抑え続けて平気なのだろうか? ある日突然、何かのきっかけで感情のダムが決壊することはないのだろうか?
二人がそんな話をしていると、突然、遠くから甲高い声が響いた。静寂の村では珍しいほどの声量だ。そちらの方向を見やると、一人の少女が転んでしまい、痛みに耐えきれず泣きじゃくっている。周囲の大人たちは、オロオロとするばかりで、誰も彼女を抱き起こすでもなく、ただ小声で「大丈夫?」と囁くだけだ。
イオは迷うことなく駆け寄って、少女に手を差し伸べた。
「大丈夫かい? 痛かったね……」
そう言いながら、イオは少女の手をとり、優しくさすってあげる。少女は泣き顔のまま見上げ、「うん……」とか細い声を漏らす。すると周りにいた大人の一人が、申し訳なさそうに言った。
「ありがとうございます。うちの村じゃあまり感情を外に出すことはなくて……私たち、どう声をかけていいか……」
その言い訳めいた言葉に、イオは憤るでもなく、ただ穏やかに微笑んで答える。
「気持ちはわかります。でも、痛いときや悲しいときは、誰かにそれをわかってもらえるだけで救われる。泣くことや叫ぶことは、人間が自分の思いを伝える大切な手段だと思うんですよ。」
その言葉を聞いて、カイは胸の奥で何かがはじけるような衝撃を覚えた。感情を表に出さないことが“美徳”とされてきた村で、生まれて初めて「感情を肯定する言葉」を耳にした気がする。それは、村の価値観を大きく揺さぶる可能性を秘めている。
少女はイオの言葉を聞いて、少しだけ泣き止むと、自分から小さくお礼を言った。周囲の大人たちも戸惑いながら、ゆっくりと少女を支え起こす。その場の空気は気まずさと戸惑いに満ちていたが、カイはむしろその瞬間、わずかながら“救い”のようなものを感じていた。
――感情が抑えられるだけの世界では、人々はこうして心を通わせる機会を失っていたのかもしれない。